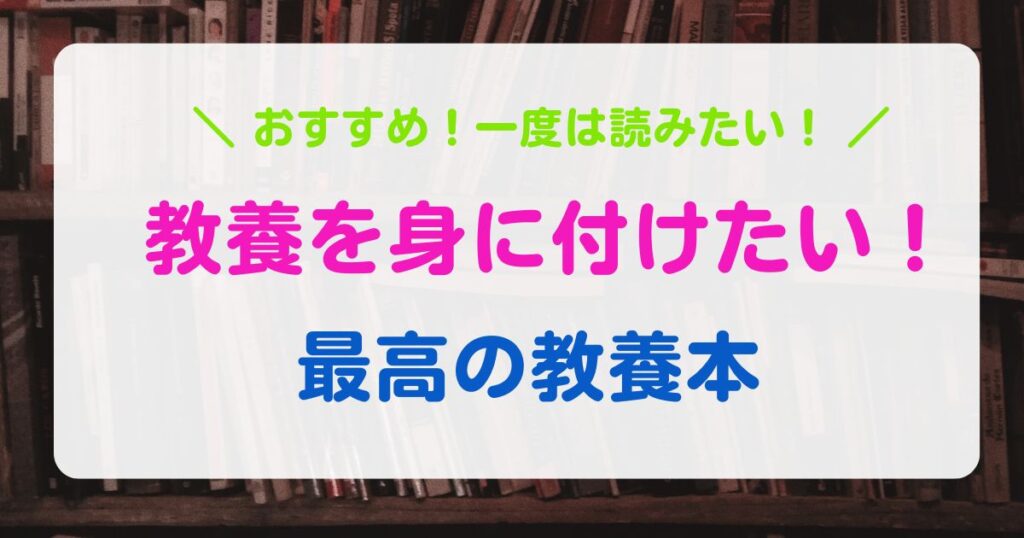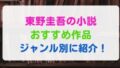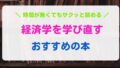社会人や大学生の方で、
- 読書量が少ない気がする
- 教養が無くて話に深みがない
という悩みがある方は意外と多いのではないでしょうか。
私も、恥ずかしながらあまり読書をしてこなかったので、就職活動や社会人生活のときに、自分の話が膨らまなかったり、考察を深めることができなくてとても苦労しました。
社会に出ると、コミュニケーション能力が高い人や話が面白い人は、十中八九で教養があって物知りです。
しかし、教養を付けたいと思っても、何から始めていいかわからないですよね。
今回は、教養を身に付けたい方向けにおすすめの教養本を紹介します。
まずはこれ!教養を学ぶ前に読みたい本
アメリカの大学生が学んでいる本物の教養
本書は、教養を身に付ける意味・身に付け方・そもそも教養とは?について書いた、教養を学ぶ際のプロローグのような本です。
何となく教養を身に付けたいけど何から手を付けていいかわからない人におすすめの本です。
- 何を学んだらいいかわからない人
- 知識の身に付け方・使い方が分からない人
- 大学生・社会人など学び直しがしたい人
教養と言っても、何を学んでいいかわからないですよね。
筆者は、教養とは専門知識・一般常識などの断片的なものではなく、自分の価値観や人生哲学を形成する幅広い知識・考え方であると述べています。
さまざまな知識・情報・考え方を吸収して、自分なりに考察・咀嚼して、自らの価値観を形成できて初めて『教養』と呼べます。
- 教養とは何か?
- 知識や情報の吸収の仕方・学び方
- 物事を思考・考察する方法
この本を読めば、教養の定義・知識を吸収する方法・知識を考察して自分の価値観に昇華する方法を明かしてくれるので、知識を「教養」として身に付ける方法が分かります。
日本人は、自分の意見がなかなか言えない…という傾向がありますが、自分の意見(=自分の軸)を持って議論を積極的にできるようになるには、教養を身に付けることが必要です。
この本で、自分の軸・価値観を形成する方法を身に付ければ、主体的考えながら生きることができます。
教養を身に付けるための本を探せる本
英国エリート名門校が教える最高の教養
本書は、英国の名門パブリックスクールへの受験講師である筆者が、パブリックスクールで学ぶ教養はどういうものかについて述べた本です。
パブリックスクールとは、英国の名門中高一貫校で、多くの卒業生は名門大学に進学し、歴代首相など多くのエリートを輩出している学校です。
いまいちイメージがわかない方は、パブリックスクールは、ハリーポッターのホグワーツ学校のモデルになったので、その雰囲気をイメージしてみてください。
この本では、そのパブリックスクールで学習する、
- 教養の学び方
- 必読すべき教養書
について、詳しく知ることができます。
- 世界のエリートが読んでいる教養本を知りたい人
- エリートの教養の身に付け方を知りたい人
特に、海外の学校では、ほとんどの学校でエッセイを書かせる習慣があり、試験でもエッセイが多く課されます。
したがって、教養とはまずは正しい文章が書けることであるとし、パブリックスクールでは、文章の書き方を学びます。
この本では、パブリックスクールで学べる、論理的で知的な文章を書く方法やエッセンスが具体的に紹介されています。
教養とは、ネットなどですぐに調べられるような知識を指すのではなく、過去の思想や考え方・物事の捉え方を学ぶことだと思います。
その考え方を基に、自分なりの考え方を構築することが大切であり、その思考の整理と表現がエッセイというわけです。
小手先の知識ではなく、じっくりと教養を培いたい人におすすめの一冊です。
- 教養の基礎となる世界的名著
- 世界のエリートの教養に対する考え方
世界のエリートが学んでいる教養書必読100冊を1冊にまとめてみた
本書は、社会人として読んでおきたい教養書100冊を1冊に要約した本です。
基本的な教養を身に付けたいけど何を呼んだらいいかわからない人や、ざっくりと教養を幅広くに身に付けたい人におすすめの本です。
- 何の教養本を読めばいいかわからない人
- 幅広くまんべんなく教養を身に付けたい人
- 自分に興味のある教養分野を知りたい人
教養と言っても分野が広すぎて、何から学べばいいのかわかりませんよね。
この本では、
- 西洋哲学
- 東洋思想
- 政治・経済・社会学
- 歴史・アート・文学
- サイエンス
- 数学・エンジニアリング
の6分野に分けて、著名な教養本を紹介しています。
他の本だと、西洋哲学(ソクラテスやプラトンなど…)を中心に紹介するものが多いと思います。
しかし、この本では、基本となる西洋哲学から、近年話題のAIの教養書を含めた数学・エンジニアリングの分野まで網羅しているので、とても広範囲の教養を学ぶことができるのが利点です。
全部で約700ページ近い分量の多い本になりますが、満遍なく教養をひととおり付けたい人は最初から読むのもいいですし、興味のある分野が決まっている人はその章を重点的に読んでもいいと思います。
この本では、教養本の要点やエッセンスを紹介するとともに、おすすめの和訳・意訳本を紹介してくれているのが助かります。
さすがに、例えばヘーゲルの精神現象学を原書を読むわけにはいかないので、筆者は、その原書をわかりやすく和訳した本や解説本を合わせて紹介してくれているため、明日からでもその教養本に取り組むことができます。
また、私たち現代人・ビジネスマンがその教養本から教訓にできることを抽出してくれている点もとても分かりやすいと思います。
- 社会人として読んでおくべき教養本
- 先人・歴史から教訓にできること
物事の考え方を学べる本
世界のリアルは「数字」でつかめ!
この本は、「人々・国々・食・環境・エネルギー・移動・機械」の7分野について、数字やデータを基に、人々の盲信や常識を覆したり、新しい視点を与えてくれる本です。
全部で71トピックスありますが、ボリュームがあって分野も広いので、雑学や教養として学べるとともに、データをどう読んで組み立てるのかという考え方を身に付けることができます。
- 教養や常識をバックデータと一緒に学びたい人
- 世界の事象について新しい視点で学びたい人
データに基づく教養本ですが、「こういうデータがあるから●●だ」と事実を突っぱねるような感じではなく、「データは使う人によって恣意的に使われるので、なるべく客観的にデータを捉えよう」と言う視点から、物事は1つのデータから様々な観点で理解できる、という論調で述べています。
また、具体例を多く用いていて、1つのトピックが4ページほどで短いので、読みやすい・理解しやすいのが特徴でスラスラと読めます。
- 世界の物事のデータの裏付け
- データから考察する方法