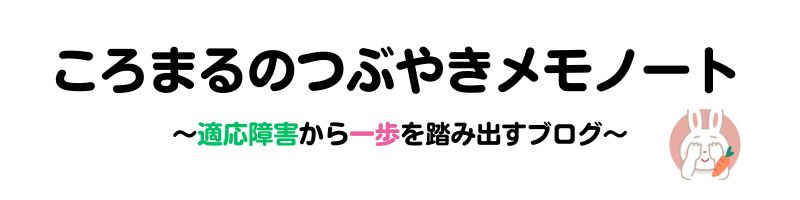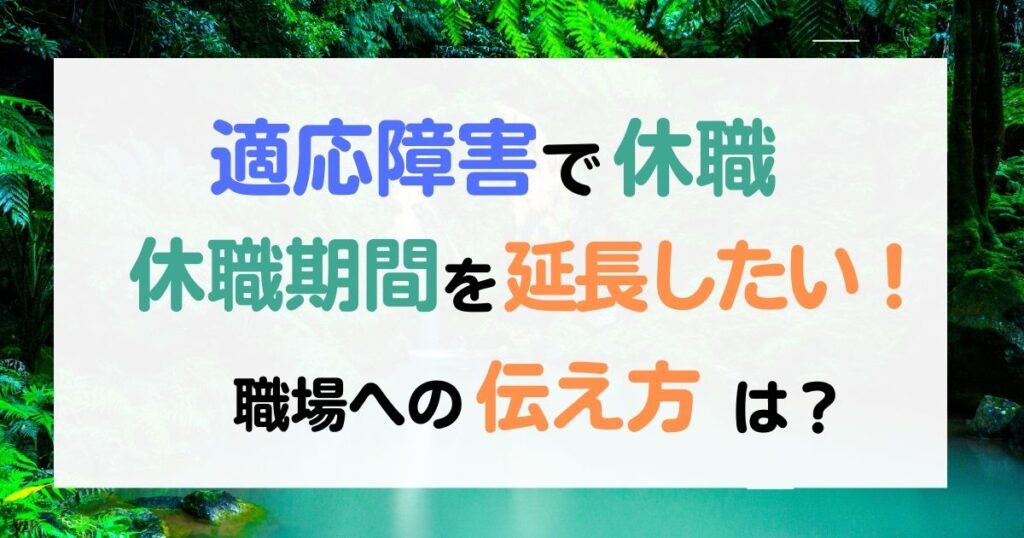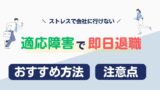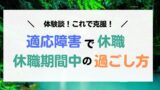適応障害で休職中の方で、なかなか体調が治らないので、休職を延長したいと思っている方もいると思います。
今回は、休職を延長したいけど、
- 職場への休職の伝え方がわからない
- 連絡方法は電話じゃないとだめなの?
- メールの例文が知りたい
という不安や悩みを抱える方向けに、記事を書きました。
私も適応障害を発症して、休職期間を延長しましたが、最初はどうやって連絡していいかわからずもやもやしました。
適応障害の休職期間の延長について職場に伝えたいけれど、電話やメールなどでどのように伝えていいかわからない方は、ぜひ参考にしてください。
適応障害で休職期間を延長する方法や手続きの流れが知りたい方は、こちらの記事で紹介しているので参考にしてください。
休職期間の延長の伝え方
休職期間を延長する際には、ほとんどの場合、休職期間が過ぎる前に、上司や人事から「その後の体調はどうですか。」と連絡が来ます。
職場からどういった方法で連絡が来るかにもよりますが、休職期間の延長の意志を伝える方法は、電話又はメールになります。
しかし、電話(メール)で伝えなければならないという決まりはないので、自分に合う方法で連絡しましょう。
まずは、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。
電話で伝える
まずは、電話で伝える場合です。
- 自分の近況を詳しく説明できる
- 復職後のことを多少なり相談できる
- 職場の人と直接話す必要がある
電話で伝えると、直接話ができるので、自分の症状や復帰などの意志について詳しく説明することができます。
特に、いずれは復職をしたいと強く考えている人は、電話で話すことで、現時点では復職が難しくても、復職した際の配置などについて事前に相談できます。
ただし、職場の人と直接会話をする必要があるので、そもそも職場にストレスを抱えている方は、電話をするだけでも気持ちが辛くなってしまうかもしれません。
メールで伝える
次に、メールで伝える場合です。
- 職場と直接やり取りする必要がない
- 必要最小限のやり取りで済む
- 職場と関係が疎遠になる
メールで連絡する場合は、職場の人と直接会話をする必要がなく、メールの文面のみのやり取りになるので、必要最小限の対応で済ませられるのがメリットです。
特に、職場の人と関わるのが非常にストレスに感じていて、職場となるべく関わりたくない場合には、メールでのやりとりをおすすめします。
私も、メールで上司とやり取りをしましたが、会話をしなくていいので、根掘り葉掘り状況を聞かれたり、余計な話をする必要がなかったので、ストレスフリーで対応できたのがよかったです。
ただし、メールで伝える場合には、「休職期間の延長」のみの話となるので、それ以外の話がしづらく、職場と関係が少し疎遠になってしまいます。
もし、少しでも復職の意志があり、復職後に気持ちよく円滑に復帰したい場合には、電話で連絡するのがおすすめです。
電話でもメールでも伝えたくない場合
職場と一切連絡を取りたくないので、電話でもメールでも伝えたくないという方もいるかもしれません。
休職期間を過ごして、やっと少し症状が改善されたところで、また職場とやり取りをして辛くなるのが怖い…と感じてしまうのは自然なことです。
職場に休職の連絡をしたくない場合には、退職をするのも1つの方法です。
というのも、
- 退職しても引き続き傷病手当金はもらえる
- 退職すれば職場と縁が切れる
- 心機一転して次の目標を目指せる
ので、復職を目指さないのであれば、特段無理に在職にこだわる必要はありません。
休職の延長をするたびに、職場への連絡にストレスを感じるのであれば、退職してもいいと思います。
退職する際には、職場に直接は伝えにくいと思いますので、退職代行サービスを利用して、代わりに退職の意志を伝えてもらいましょう。
職場とは一切関わらずに退職できますし、退職後の傷病手当金の手続きの流れなどの事務手続きも確認してくれるので、確実にトラブルなくすっきりと退職手続きを済ませられます。
退職代行サービスを選ぶ際には、退職代行CLEARのような、合同労働組合が運営している会社で、かつ、依頼料が業界内で安いサービスを選びましょう。
こちらの記事に、おすすめの退職代行サービスを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
休職期間延長の連絡する際に伝えるべきこと
休職期間を延長する際には、次のこと確実に伝えるようにします。
- 休職の延長の意志があること
- 医師から診断書が発行されたこと
- 休職を延長する期間
休職の延長の意志があること
休職期間は自動で延長されません。
自分は休職期間を延長して休職したい、と職場に明確に伝えましょう。
たまに、症状などを詳しく伝えるものの、肝心の休職についてどうするのかを伝えそびれる方もいるので、はっきりと「休職したい」と明示的に示すことが大切です。
医師から診断書が発行されたこと
休職の意志があっても、診断書がなければ休職ができません。
医師から、「症状が改善されないので、引き続き適応障害で療養の必要がある」という診断書をもらいました、と伝えます。
診断書が手元にあることを伝え、どこに診断書を送付すべきか(決まっている場合には送付する旨)を確認します。
休職を延長する期間
最後に、休職を延長する期間を伝えます。
診断書に記載されている期間をそのまま伝えれば大丈夫です。
メールで伝えるときの例文
メールで伝える際の例文を載せておきます。
上司から休職の延長の有無について連絡があった際に、それに返信する形でいいと思いますが、万が一、会社から連絡がない場合には、次のようなメールを上司や休職手続の窓口になっている担当者に送付しましょう。
●● 様
お世話になっております。
●●です。
休職手続の件で連絡いたしました。
先日心療内科を受診したところ、引き続き「適応障害」で療養が必要との診断がありました。
症状が改善されないので、引き続き休職をさせていただきたく存じます。
診断書を送付いたしますので、ご査収のほどお願い申し上げます。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
●●
ぜひ活用してください。
休職期間を延長して充実した時間を過ごす
休職期間を延長するには、職場に連絡することが不可欠です。
しかし、延長の連絡はあくまで手段であり、その後に、延長された休職期間をどう過ごすかの方がもっと重要です。
休職延長をした際に気を付けるべきことを2点紹介します。
休職後のことを考える
休職期間は何度も延長できるわけではありません。
企業の就労規定で定められている休職期間を満了した場合には、職場復帰か退職するかの選択をする必要があります。
休職期間中は、体調が芳しくないので、休職後のことについて考えるのはなかなか難しいかもしれませんが、休職期間を終えた後に職場に戻りたいかどうかだけでも検討しておきましょう。
職場に戻る意思が低い場合には、退職後のことも考えておく必要があります。
退職後は失業保険を受給できますが、満額受給するには、失業前からの準備が必要です。
まずは、無料セミナーで失業保険について知識を付けると何をすべきかがわかり、余裕をもって準備ができます。
また、休職中に、転職についても検討を始めておくと安心ですね。
休職期間の過ごし方を工夫する
休職期間は、体調を回復するのはもちろんですが、まとまった貴重な時間が取れるので、資格の勉強など普段できないことにチャレンジするのにとてもいい機会ですね。
休職期間のおすすめの過ごし方は、こちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。